JR 東西線 大阪天満宮駅東行(3番出口)徒歩1分
(JR
環状線 天満駅ではありませんので注意してください)
(地下鉄谷町線・堺筋線 南森町から、4a出口より、まずJR連絡口へ)
※
当ビル内に立体駐車場(有料:200円/30分)はございますが、
車体制限(高さ1.55M,幅1.75M,長さ5.05m)に、ご注意ください。
ちょっと待て!本当に良いのか?その示談 南森町佐野法律特許事務所は,交通事故を専門としています。
TEL. 06-6136-1020
〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205
南森町佐野法律特許事務所は、交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。
5 後遺症
5−2 後遺障害に対する賠償(補償)について
5−2−4 後遺障害の認定方法
- 1.後遺障害について
2. 後遺障害に対する賠償・補償
2-1.後遺症慰謝料
2-2.逸失利益
2-3.計算方法
2-4.後遺障害の認定方法
2-4-1.認定の手続
2-4-2.手続の流れ
2-4-3.注意すべきこと
2-4-4.示談の後に
2-4-5.確認すべきこと
後遺障害の認定の手続
後遺障害の認定の手続は、概ね次のとおりです。
被害者又は加害者→(診断書を添付して書類を送付)→ (自賠責)保険会社(自賠責)保険会社→(書類を送付)→損害保険料率算出機構
損害保険料率算出機構が調査
損害保険料率算出機構→(調査結果を報告・後遺症の有無などを認定し通知)→(自賠
責)保険会社・被害者
手続きの流れ
手続きは、 まず、被害者あるいは加害者から、医師の診断書を添付して保険会社に請求し、保険会社は、受取った書類を 損害保険料率算出機構 (旧称、自算会)に送ります。損害保険料率算出機構は、調査をし、調査結果を保険会社に報告します。保険会社は調査結果に基づき認定をします。
注意すべき事
医師の診断書が必要なことをいいことに、診察費の外に金銭を受け取り、み返りに患者に有利な診断書を書く医師がいます。被害者から金銭の提供を提案する場合が多いようですが、日本の医師の状況を見ていると嘆かわしい次第です。
また,日本の医師は,大学で,後遺症診断書の書き方を勉強したわけではなく,あくまでも,治療方法を学んだに過ぎません。そのため,後遺症診断書の書き方を勉強する場もなく,医療現場に出てきた医師が殆どです。
不幸なことに,後遺症診断書の書き方に習熟していない医師が主治医であった場合,折角,上位の後遺症の等級が認められて然るべきであるのに,下位の等級しか認められなかったり,また,等級外になってしまうことが多々見受けられます。
本来,後遺障害の診断書に関しては,医師の専権事項であり,弁護士が口を出すわけにはいかないのですが,自賠責に,等級認定する前に,交通事故について知識のある弁護士に,一度,後遺症診断書を見てもらった方がよいでしょう。不都合な点や不合理な点については,医師に修正してもらうべきです。
示談の後に
一度示談ができてから後に後遺障害が発生した場合に、さらに後遺障害につき損害賠償請求できるかが、よく問題となります。これについては、最高裁判所の判決(昭和43・3・15)があり、示談当時発生していない、予想できなかった後遺障害については、その後さらに損害賠償の請求ができるとなっています。しかし、示談が成立した後に、生じた後遺障害を請求することは実務上非常に困難です。
確認すべきこと
従って、示談は、後遺障害の発生がないことを確認してからすべきです。しかも、後遺障害について示談するには後遺症が固定してからでないとできません。
よって、損害賠償請求の時期は、慎重にすべきです。
-
交通事故 ちょっと待て,本当に良いのか,その示談
- 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。
南森町佐野法律特許事務所は,交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。
- 〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205
電話 06−6136−1020
FAX 06−6136−1021
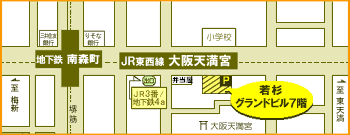
- 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。
-
NEWS新着情報
- 2011年7月18日
- 交通事故のサイトをオープンしました。
- 2010年12月 日
- 読売放送(10ch)に登場しました。
- 2011年*月*日
- サイトを更新しています。